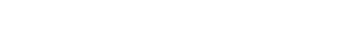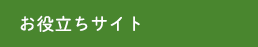「全国賃貸不動産管理業協会」作成【家族信託(民事信託)について其の二】
前回に引き続き今回は其の二~【まず、信託の種類】から。
まず信託には『民事信託』と『商事信託』とがあります。世間一般で馴染みの有ります「信託」とは信託業法で規制された受託者、主に信託銀行が扱っております「信託」のことと思います。
当然ですが「商事」という言葉が付いていますので「報酬(営利が目的のため)」が必ず存在します。
今回記載して参ります内容は、商事信託では無く「民事信託」のお話です。
商事信託には「信託業法」という法律の適用がありますが、誰でもが受託者となれる「民事信託」には信託業法の適用はありません。
民事信託とは「家族のために行う信託」とも言えますので、最近皆様が良く耳にします【家族信託】などとと呼ばれている所以かと思われます。
【では、家族信託制度ご存知ですか】
以前にも本ブログで多少はご紹介をさせて頂いたことがございました。今後のオーナー様にとりましては大変重要なテーマだと信じていますので、今回、再度ですが記載して参りたいと考えました。
何故なのか?
オーナー様が、長年にわたり苦労されながら築いてこられました「資産」を、ご自身の代ではもちろんの事ですが、今後も引き続き継続して頂けるための対策に成り得るものと考えています。但しですが、この家族信託ダケ行っていれば全て
【オーナー様の気持ちを「資産(財産)」に反映させる事が出来るために】
☆民事信託(家族信託)という制度が出来る前までは☆
前回の「その①」オーナー様が万が一ですが、賃貸住宅経営の現場で(認知症などで)資産(財産)が凍結になってしまう原因は
少子高齢化の「高齢化」の現象が現れるわけですね。
従来ですと「後見人」制度を活用し、例えば長男の方が後見人となる道がありました。
しかし、後見人には別に「監督人」が家庭裁判所から選任をされ後見人を監督をすることになります。
後見人は現在の資産(財産)をただひたすら保全するダケの行為しか許されません。
新たな投資・借金・不動産購入等は全てNGですので、所有者様が亡くなるまで一切手を付けることが出来なくなります(改善も含めた)
従いまして完全に「凍結状態」となってしまいます。
【家族信託の考え方】
信託とは簡単に申しますと「信頼する人に行為を託す」ということと思います。
そして私が考えます最大の利点は「自分の意思が反映出来る」ということと考えます。
要は自分が「意思表示」が出来なくなった時、誰に「運営」を任せて、自分の意思を反映させるかの選択と思います。
託す資産(財産)は種々有りますが今回は「不動産(賃貸住宅)」がテーマです。例を挙げていきたいと思います。
オーナーA様は自分の今後の事を考えた末、長男Bと「信託契約」を締結することにしました。
ここで、信託契約時に於けます各人の呼称につき説明したいと思います(賃貸住宅の信託契約)
@オーナーA様(お願いする人)=委託者と呼びます。
@長男B(お願いされた人)=受託者と言います。
@運営益を受ける人=受益者と言います。
⁂通常は委託者=受益者となるのが普通の考え方と思います。
【信託契約すると謄本上はどうなるのか】
委託者A、受託者B、受益者Aとして賃貸住宅の信託契約が締結されたと仮定します。
この時、賃貸住宅の「所有権」は名義と受益権の2つに分かれます。名義は長男Bに渡り受益権がAに生じます。
登記権利者は長男Bなのですが移ったのは「名義」ダケなので、この段階での税金(贈与税等)の発生はありません。
【信託契約のメリットは】
仮に契約締結後に委託者Aが意思表示が出来なくなった場合、受託者B(長男)の判断にて、このまま運営していくのか、それとも委託者Aのために売却し何等かの費用に充てるのかが可能となります。
結果「凍結状態」が回避されることとなります。
【万一心配であれば】
信託契約の内容ですが全てOKという事も当然可能ではあるのですが、「此処まで」とか「この事と、この事」というように委託する内容の限定も可能です。
ご自分の「目の黒いうち」にどうするのか!?を反映出来る方法の一つと考えます。
|
|
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫 |
| 1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。 |